- 1. はじめに
- 2. 省エネ計算の新制度の全体像
- 2.1 新たな義務化の内容とは?
- 2.2 登録制度の対象範囲と流れ
- 2.3 計算書と根拠図書の提出義務
- 3. WebプログラムVer.3.7のポイント解説
- 3.1 旧バージョンとの違い
- 3.2 操作フローと出力帳票
- 3.3 新たなUIと注意点
- 4. 設計実務で注意すべきポイント
- 4.1 根拠資料としての図面整備
- 4.2 入力ミス・誤認識が多い箇所
- 4.3 完了検査で問われる視点
- 5. 登録・提出の流れ(Step by Step)
- 5.1 必要書類一覧
- 5.2 提出先と登録先の違い
- 5.3 設計士の役割と留意点
- 6. よくある質問とその回答(FAQ)
- 7. まとめ:設計士が今すぐ準備すべきこと
- 8. 参考リンク・資料
2025年4月、建築物の省エネ計算において「義務化」と「登録制度の開始」という大きな制度改正が施行されました。 設計実務の中で、これまで以上に省エネ計算書の提出と根拠図書の整備が求められるようになっています。
特に、Webプログラム(Ver.3.7)の更新により、入力項目や出力帳票、提出様式にも多くの変更が加わっており、 設計士・建築士が従来の感覚で進めると、思わぬ不適合や差し戻しを受けるリスクもあります。
本記事では、今回の改正の全体像と、最新のWebプログラムの使い方、図面・計算書の整備ポイントを、 設計者目線でわかりやすく解説していきます。 「結局、何を準備すればよいのか?」が明確になる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
2025年4月から施行された建築物省エネ法の改正により、新築住宅における省エネ基準への適合義務が全国でスタートしました。
これまで「努力義務」とされてきた省エネ計算が、建築確認申請と連動する法的要件となり、 全ての新築戸建住宅・共同住宅は、原則として省エネ基準に適合していることを確認しなければなりません。
あわせて、2025年4月以降は、登録住宅性能評価機関などによる省エネ適合性判定が本格運用されており、 設計者はこれに対応するため、所定の計算方法や帳票の整備、図面への記載内容にも十分な注意が必要です。
▼ 今回の制度改正で求められる主な対応:
・建築確認前に省エネ基準適合性の確認が必要
・Webプログラム(Ver.3.7)等を使った適正な計算書作成
・外皮性能(UA値・ηAC値)と一次エネルギー消費量(BEI)の確認
・提出用図面への根拠記載やチェックリストの整備
このように、設計初期から省エネに関する計算と書類整備を意識することが求められる時代となりました。 次章では、省エネ計算に用いられる主要な指標について、それぞれの意味と役割を解説していきます。
2025年(令和7年)4月から、全ての新築住宅に対して省エネ基準への適合が義務化されました。 これまでは一定規模以上の非住宅建築物が対象でしたが、今回の改正により、戸建住宅や共同住宅も義務化の対象となった点が大きな変更点です。
具体的には、設計段階で「外皮性能基準(UA値)」と「一次エネルギー消費量基準(BEI)」の両方を満たす必要があります。 これにより、建築士や設計事務所は省エネ計算の提出・適合確認を前提とした設計が求められるようになりました。
▼ 省エネ基準義務化のポイント:
・すべての新築住宅が対象(300㎡以下も含む)
・建築確認時に「省エネ適合性判定書」が必要
・確認申請時に提出しないと、着工できない
これにより、設計初期からの省エネ対応が必須となり、断熱・設備・開口部の選定においても「基準を満たすこと」が最優先になります。 次のセクションでは、この義務化に対応するうえで、なぜηAC値のような“冷房期の指標”が重要視されてきているのかを解説していきます。
2025年4月より、延べ床面積10㎡超の新築・増改築建築物すべてが、省エネ基準(外皮性能+一次エネルギー消費量)への適合義務に含まれます。住宅・非住宅問わず、確認申請では「省エネ適合性判定書」の添付が必要です。
● 制度対象の範囲
- 延床面積10㎡超の新築・増改築建築物すべて
- ただし、10㎡以下の小規模建築物や非居室・高開放建築物、歴史的建築物などは除外
● 適合性判定の手続きの流れ
- Webプログラム(Ver.3.7等)を用いて省エネ計算および判定データを作成
- 所管行政庁または登録省エネ判定機関へ「省エネ適合性判定」を申請・提出
- 適合判定通知を受領し、確認申請書類に添付
- 完了検査時にも適合性が確認され、不適合の場合は検査済証が交付されません
増改築では、増改築部分のみが適合判定の対象となります。既存部分が基準未満でも、増改築部分が基準を満たせばOKです。
所管行政庁によっては、省エネ適判の審査を登録判定機関に委任する制度を導入しており、自治体ごとの提出先や手順を事前に確認することが重要です。
2025年4月以降、すべての新築・増改築建築物に対して、省エネ基準への適合確認が義務化され、 確認申請時に省エネ計算書と根拠図書の提出が必須となりました。
加えて、完了検査時にも「計算内容と図面の整合性」が確認されるようになり、形式的な提出では通用しなくなっています。
▼ 提出時に必要な主な書類:
・外皮性能計算書(UA値・ηAC値)
・一次エネルギー消費量計算書(BEI)
・各種図面(平面図・立面図・矩計図など)
・仕様書・計算条件表(断熱材・窓・空調設備など)
特に注意すべきは、設計変更に伴う図面と計算内容の不一致です。 確認申請後に仕様変更があった場合、それを計算書や根拠図面に反映していないと、完了検査で差し戻しになるリスクがあります。
そのため、設計者・計算者・施工者が常に情報を共有し、最新の設計内容をもとに提出図書を整える体制が不可欠です。
2025年4月の法改正に伴い、省エネ計算のWebプログラム(住宅・非住宅版)がVer.3.7にアップデートされました。 この変更により、設計実務における操作画面や出力帳票の仕様が大きく変わっています。
以下では、Ver.3.7で特に重要となる変更点を整理し、設計者が注意すべきポイントを明確に解説します。
▼ 実務で押さえるべきポイント:
1)UIが刷新され、ステップ形式の入力に対応
2)エラー表示が強化され、入力ミスが即時に明示
3)住宅と非住宅で仕様が完全に分離し、プログラム選択が必要
4)XML出力や登録システム連携など制度対応が必須化
これらの変更により、操作性は向上した一方で、制度との整合性を前提とした入力・出力の流れが求められるようになりました。
次の章では、旧バージョンとの違いを比較しながら、操作画面や帳票の具体的な変更内容を紹介していきます。
WebプログラムVer.3.7は、これまでのVer.3.6以前と比べて、操作性・出力帳票・整合性チェック機能の3点において大きな見直しが行われました。
以下では、実務者が特に把握すべき主な変更点を整理しています。
▼ 主な変更点:
1)入力画面の刷新: 部位や仕様の入力が階層的に整理され、操作の流れが明確化
2)出力帳票の変更: 外皮面積表や計算結果に、根拠図面との対応を意識したレイアウトを採用
3)チェック機能の強化: 未入力や不整合があると計算書出力が不可。制度適合を前提とした運用に
これにより、旧バージョンと比較して操作の自由度は下がったものの、計算結果の信頼性や制度適合性を担保する設計となっています。
とくに旧バージョン(Ver.3.6)に慣れている場合、同じ感覚で進めると意図しないエラーや出力ミスに戸惑う可能性が高いため、 一度操作手順を見直し、事前に入力方針を整理してから着手することを強く推奨します。
WebプログラムVer.3.7では、従来の操作フローが再設計され、 登録システムとの連携を前提とした入力・出力の手順が必須となりました。
以下に、実務で押さえるべき基本フローと出力帳票の種類をまとめます。
▼ 操作フローの全体像:
① 建物情報の入力(構造・階数・地域区分など)
② 外皮性能の設定(部位・断熱材・窓など)
③ 一次エネルギー消費量の入力(空調・給湯・照明)
④ 結果の確認とPDF帳票の出力(整合性の事前チェック)
⑤ 登録用XMLファイルの作成(提出用データ)
⑥ 登録システムへのアップロード(正式な帳票取得)
▼ 出力される帳票の種類:
・確認用PDF:設計段階のチェック用
・登録システム出力PDF:正式な適合判定用書類
・参考帳票:BEI計算や削減量の補足資料
特に2025年からは、登録用XMLの作成とアップロードが制度上の必須ステップとなっており、 これを前提とした操作が必要です。
従来のようにPDF出力だけで完了とはならないため、帳票の種類ごとの用途と連携先をしっかり理解しておくことが重要です。
WebプログラムVer.3.7では、操作画面のUI(ユーザーインターフェース)が全面刷新されました。 ステップ形式のナビゲーションが導入され、入力の流れが明確になっています。
ただし、制度と連動した操作構造となったことで、操作性の向上と同時に新たな注意点も生まれています。
▼ 新UIの特徴と注意点:
・ステップナビ形式で、入力の順序が明確に案内される
・画面左に「入力サマリー」が表示され、進行状況を把握可能(※保存忘れに注意)
・PDF出力後、「登録システムへ」ボタンでXMLファイルを生成(提出用)
・未入力やミスがあれば即赤色で表示され、修正ポイントが明示される
このようにUIは進化しましたが、「出力した帳票=提出OK」ではないという点には注意が必要です。
特に省エネ適判や届出においては、登録用XMLを経由して出力されたPDF帳票が正式な提出書類とされるため、 新しい操作フローを正確に理解し、制度の要件に沿った使い方を実践することが求められます。
2025年の省エネ制度改正により、設計士が対応すべき実務範囲は大きく広がりました。 単なる計算ソフトの操作だけではなく、図面・帳票・検査との一貫性を意識した対応が求められています。
特に重要なのは、次の3つの視点です。
▼ 実務での重要ポイント:
① 図面上での根拠記載(どの部位をどう計算したかを図示)
② 計算内容と提出資料の整合性(入力と帳票が一致しているか)
③ 現場・完了検査との整合(実際の施工と帳票に齟齬がないか)
これらの対応が不十分だと、指摘・差し戻し・補助金の対象外など、さまざまな実務リスクにつながります。
省エネ計算は「計算書を出すだけの作業」ではなく、設計業務の一環として根拠・整合・説明責任を伴う業務であるという意識が必要です。
次のセクションでは、これらの中でも特に重要な図面の整備方法について、具体的な対応例を解説していきます。
2025年4月以降、省エネ適合性判定においては、「図面に省エネ計算の根拠が明記されていること」が非常に重要となりました。 帳票の数値だけでは不十分とされ、審査機関や補助金事務局では図面上での根拠確認が求められます。
特に次の図面に、根拠を明確に記載することが推奨されます。
▼ 根拠記載が必要な主な図面:
・平面図:サッシ面積、方位、部屋名称の記載
・立面図:方位、庇・袖壁の出寸法などの日射遮蔽要素
・矩計図:断熱材の仕様・厚み・位置の明示
・建具表/仕様書:開口部のガラス種別や性能値
たとえば、開口部面積やLow-Eガラスの種類、庇の出寸法などが、 Webプログラムに入力された内容と図面で食い違っている場合、審査で差し戻される可能性が高くなります。
そのため、「どの仕様で、どの部位を、どう計算したか」が図面から読み取れる状態にしておくことが、 適合審査や補助金の通過、完了検査の円滑化に直結します。
Webプログラム(Ver.3.7)での入力においては、設計図との読み違いや思い込みによる誤入力が原因で、 BEI不適合・差し戻しといった事例が多発しています。とくに以下の項目は、ミスが起きやすいため注意が必要です。
▼ 入力ミスが頻発するチェック項目:
・開口部面積の取り違え:図面の実寸ではなく、建具表の数値をそのまま転記してしまう
・庇・袖壁の未入力:立面図に記載があるのに遮蔽要素として反映されていない
・屋根断熱と天井断熱の混同:部位の断熱仕様に応じた正しい選択が必要
・床下の扱い:ベタ基礎+床断熱などの条件で入力区分を誤るケースが多い
・部屋用途の選択ミス:居室/非居室で内部発熱条件が異なり、BEIに影響
特に多い誤認識: 図面の「北」を上と仮定して方位を入力してしまうケースがあり、ηAC値が不自然な数値になることがあります。 必ず、図面に明示された方位マークを確認し、窓の配置や面積と整合する形で入力してください。
小さなミスでも適合判定全体に影響するため、根拠図面との照合作業や二重チェック体制が非常に有効です。
2025年4月以降、完了検査時に省エネ基準への適合状況が実質的に確認されるケースが増加しています。 特に、提出された省エネ計算書と現場施工の整合性が重要視されており、以下の視点でチェックされることがあります。
▼ 完了検査で問われる主なチェック項目:
・窓ガラスの仕様:Low-Eガラスの種類(遮熱/断熱)と計算内容が一致しているか
・庇や袖壁の有無:ηAC値に影響する要素が図面どおりに施工されているか
・断熱材の厚み・材質:計算書・仕様書どおりの断熱性能が確保されているか(天井・壁・床)
・換気設備の確認:第三種/第一種などの換気方式に対応する設備が設置されているか
・日射遮蔽の工夫:外付けブラインド・植栽などの遮蔽要素が現場にあるか
確認検査機関によって対応には差がありますが、設計内容と著しく乖離がある場合には是正・再提出を求められることがあります。 よって、図面と計算書の整合性を設計段階から確保し、施工時にも反映させる体制づくりが不可欠です。
2025年4月の制度改正により、省エネ計算に関する「登録」と「提出」の役割・手順が明確に分けられるようになりました。 特に住宅設計においては、設計士がいつ・何を・どこに提出すべきかを正しく理解しておくことが不可欠です。
このセクションでは、登録制度の実務フローを以下の3つの視点に整理して解説します。
▼ 手続きの3ステップ:
① 必要書類一覧(何を準備すればよいか)
② 提出先と登録先の違い(どこに提出・登録するのか)
③ 設計士の役割と留意点(実務上の注意ポイント)
本章は、準備漏れや提出ミスを防ぐチェックリストとしても活用できます。 登録・提出に関わる一連の流れを明確に把握し、スムーズな手続きを進めましょう。
2025年4月の制度改正により、省エネ計算に関する提出書類の標準化・明確化が進みました。 本セクションでは、住宅・非住宅を問わず共通して求められる代表的な提出書類を一覧形式で整理しています。
以下は、適合判定や各種申請において一般的に必要とされる基本書類です。
▼ 提出書類一覧(住宅・非住宅 共通):
① Webプログラム計算結果報告書(PDF):
最新Ver.3.7で出力された「適判用PDF」が必須。
② 登録用XMLファイル(.mxl形式):
電子登録制度に対応。PDFのみでは提出不可。
③ 根拠図書一式:
平面図・立面図・矩計図・断面図・建具表などの図面類および仕様書など。
④ 住宅仕様基準表(該当制度の場合):
長期優良住宅・地域型住宅グリーン化事業等にて必要。
⑤ 省エネ計画書(エネルギー消費性能確保計画書):
確認申請に先立ち、正副2部を提出。
⑥ 設計内容説明書(任意または審査機関の指定):
計算範囲・熱源条件・削減対策等の補足情報を記載。
⑦ 建築確認申請書(第2面):
「省エネ適判済」欄への転記に使用。
⑧ その他関連書類(必要に応じて):
BELS申請書、長期優良住宅の認定書類、代理委任状、手数料納付書など。
実務ポイント:
特にXMLファイル(.mxl)は、2025年から導入された電子登録制度での必須書類です。
WebプログラムVer.3.7を使用し、正しい形式で出力・保存してください。
また、提出先ごとの指定フォーマットやファイル名ルールにも十分注意が必要です。
登録機関・審査機関・自治体など、提出先によって書式や提出要領が異なる場合があるため、必ず最新の情報をご確認ください。
2025年4月の制度改正により、省エネ適合義務への対応として「登録制度」が導入されました。 これにより、従来の「提出先」との役割の違いを正しく理解し、登録と提出を分けて対応することが求められます。
▼ 提出先(確認申請時の提出機関):
建築主事(自治体)
指定確認検査機関
→ 建築確認の手続きの際に、省エネ計算書や根拠図書を添付し、法令上の審査を受けるために提出します。
▼ 登録先(電子登録を行う新設機関):
登録住宅性能評価機関(建築物省エネ法に基づく)
→ Webプログラム(Ver.3.7)で出力したXMLファイルを用いて電子登録を実施。
登録完了後に発行される登録番号・登録票は、審査機関への提出資料の一部となります。
▼ 実務上のポイント:
提出と登録は別の手続きであり、それぞれのタイミングに注意が必要
電子登録後に発行される登録票・登録番号の提出が義務化
登録漏れや入力ミスがあると、適判審査で差し戻されるリスクがあります
つまり、「確認申請への提出」だけでは不十分となり、2025年以降は電子登録の完了が前提条件となります。 設計者として、提出先と登録先の違いを正確に把握し、計画的に対応を進めることが求められます。
2025年4月の制度改正により、省エネ計算は単なる技術的な付随業務ではなく、法令対応の中核業務として位置づけられるようになりました。 設計士は、「省エネ計算が適合していること」を確認・証明し、責任を持って提出・登録する義務を負います。
▼ 設計士が担うべき主な役割:
・省エネ計算条件(建物形状・仕様・設備)の確認と確定
・必要図面の整備(根拠図書として提出が求められる)
・Webプログラムでの計算結果の確認
・登録用XML(.mxl)ファイルの発行と提出準備
・登録票の発行と確認申請書類への添付
・不備対応・差し戻し時の修正対応
省エネ計算を外部に依頼する場合でも、設計者自身が内容を理解し、確認責任を負う立場にあることを忘れてはいけません。
▼ 設計実務での留意点:
・間取り・外皮仕様・設備仕様を早期に確定しておく
・計算者(社内または外部)と密に連携を取る
・根拠図面に必要情報を記載(外皮区画、断熱材、開口部仕様など)
・登録・提出スケジュールを確認申請と合わせて逆算
制度変更後は、設計士の理解と段取りの精度が、省エネ適合性判定の通過に直結します。 余裕をもった準備と正確な情報整理が、プロジェクト全体のスムーズな進行につながります。
2025年4月の制度改正後、省エネ計算や適合判定に関して多く寄せられる質問をまとめました。 設計実務や申請対応の現場で戸惑いやすいポイントに対して、実務ベースでの明確な回答を掲載しています。
Q1. Webプログラムのバージョンは最新でないといけないの?
はい、2025年4月以降はVer.3.7以降での出力が原則となっています。Ver.3.6以前の帳票では審査・登録を受け付けないケースがあります。
Q2. PDFだけ提出すればよい? XMLファイルは必要?
必須です。PDF帳票だけでは登録されません。XML(.mxl)ファイルは電子登録のために不可欠な提出データとなります。
Q3. 根拠図面ってどのくらい細かく書く必要があるの?
「この断熱材で、この厚みで、この窓で計算した」と分かる状態にしておくことが必要です。平面図、立面図、矩計図に加えて、建具表や仕様書への記載も推奨されます。
Q4. ηAC値が異常に高く(または低く)なる原因は?
北の向きを誤って設定している可能性があります。方位ミスにより窓配置がずれ、日射熱取得率に大きな影響が出ます。図面の北基準を必ず確認してください。
Q5. 庇や袖壁はどこまで入力すべき?
庇・袖壁が立面図に明記されている場合、それを反映して入力する必要があります。未入力だと遮蔽効果が無視され、ηAC値が不利になります。
Q6. BELSや長期優良住宅など他制度にも同じ書類が使える?
基本的に同じですが、申請制度により追加の帳票やチェックリストが求められることがあります。提出先の要領を事前に確認してください。
2025年4月の制度改正により、省エネ計算の対応が「任意」から「義務」へとシフトしました。 設計士は、法令対応だけでなく、施主への説明責任や審査機関とのやりとりにおいても、より高い精度が求められるようになっています。
このセクションでは、今すぐ実務に取り入れるべきポイントを整理して解説します。
▼ 実務で取り組むべき具体的ポイント:
① Webプログラム(Ver.3.7)への完全移行:
最新バージョンでないと、登録票の発行やMxlデータ作成ができず、登録制度に対応できません。
② 登録先と提出先の違いを正確に理解:
登録先(性能評価機関)と建築確認の提出先(確認検査機関等)は役割が異なり、混同に注意が必要です。
③ 根拠図書の整備ルールを明文化:
断熱材の部位・厚さ・施工範囲、開口部の寸法、庇の長さなど、図面への記載ルールを社内で統一しましょう。
④ 省エネ計算を外注する場合の役割分担の明確化:
外注者の出力帳票に頼るだけでなく、設計者自身が提出内容を把握・管理する体制が重要です。
⑤ 類似案件の省エネ計算のストック化:
繰り返しの多いプランについては、あらかじめ部位構成や仕様をテンプレート化しておくと効率的です。
今後も法令や運用ルールは変化していく可能性がありますが、 設計者として基本を押さえておくことで、建築確認や登録手続きにおいてスムーズな対応が可能となります。
本記事が、日々の設計業務における省エネ対応の一助となれば幸いです。
なお、省エネ計算に不安がある設計事務所さまや、外注・代行のご相談をご希望の方は、 省エネ計算ステーションにて詳細をご案内しています。 見積もりをご希望の方は、専用フォームからご依頼ください。
2025年制度改正後に対応した、省エネ計算・登録制度に関する公式情報を整理しています。
実務に直結する内容を把握するために、必ず以下の公式リンクをご確認ください。
▼ 国土交通省・法令関連:
建築物省エネ法 最新の法令(最終更新:令和7年5月22日)
脱炭素社会実現に関する法律等 改正資料とQ&A(2025年4月施行分)
▼ 建築研究所(BECC)・技術情報:
非住宅向けエネルギー消費性能計算プログラム Ver.3.8β
BECC Webプログラム&技術案内トップ
▼ 電子登録・適判関連:
登録機関一覧・適合性判定制度概要(最新版)
▼ FAQ・サポート情報:
IBEC 非住宅版 FAQ(計算仕様・入力方法等)
▼ 法令改正関連(PDF等):
令和4年度改正 建築物省エネ法の概要
令和7年4月1日施行 改正建築物省エネ法に関する政令・施行概要
すべてのリンクは2025年6月時点で確認済みで、表示不具合やリンク切れのない情報を厳選しています。
実務対応前には、リンク先の「最終更新日」や「ダウンロード可能資料」も必ずご確認ください。
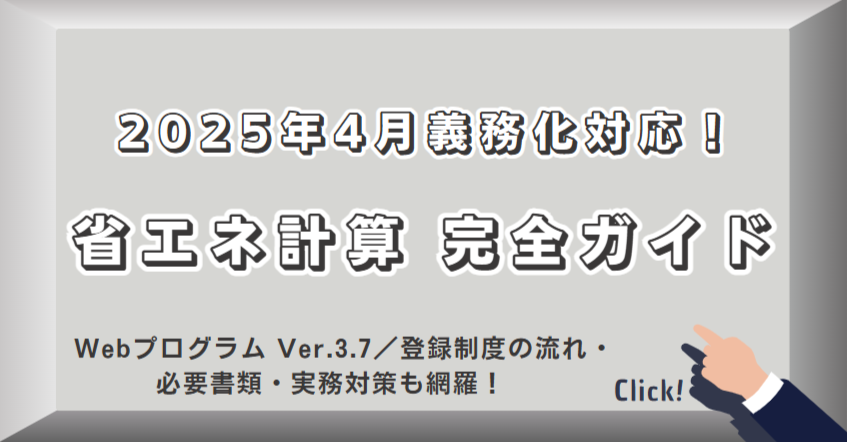
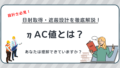
コメント