- 1. ηAC値とは?冷房期のエネルギー効率を左右する指標
- 2. UA値との違いと、なぜ両方が必要なのか
- 2.1 UA値との比較でわかるηACの役割
- 2.2 冷房負荷・一次エネに与える影響
- 3. ηAC値の計算対象と設計で注意すべき部位
- 3.1 日射取得に影響する窓・ガラス・庇
- 3.2 南面以外の注意点と簡易な見分け方
- 4. ηAC値を下げるための設計対策
- 4.1 Low-Eガラスの選定
- 4.2 庇・袖壁・外付ブラインドなどの遮蔽工夫
- 4.3 外構・植栽の活用
- 5. 等級6・7、BEIとの関係性
- 5.1 ηAC値と断熱等性能等級
- 5.2 一次エネルギー消費量・BEIとの連動
- 6. まとめ:ηACを意識した“冷房設計”がこれからの鍵
ηAC値(イータエーシー値)とは、冷房期に建物の外から入ってくる「日射熱の取得率」を数値で表したものです。
特に窓やガラスといった開口部から、どれだけ太陽の熱が室内に侵入するかが計算対象となります。
この数値が高いほど、夏場の強い日差しを多く取り込んでしまう設計ということになり、室温が上昇しやすくなります。
結果として、冷房の稼働が増え、エネルギー消費が増加します。反対にηAC値を低く抑える設計にすることで、冷房の省エネ性を高め、快適な室内環境と光熱費の削減が実現できます。
設計段階では断熱性能を示すUA値ばかりが重視されがちですが、ηAC値はその“反対側”を担う、冷房期のエネルギー効率を左右するもう一つの重要な指標です。
▶︎ ηAC値とは:
・夏の「日射の入りやすさ」を数値化したもの
・数値が高い=日差しを多く取り込む
・数値が低い=日差しを遮り、冷房負荷を減らせる
ηAC値を意識した設計は、単なる数値合わせではなく、日射遮蔽と自然の力を活かした快適な住まいづくりにもつながります。
次の章では、断熱性能を示すUA値との違いや、なぜηAC値も同時に見なければならないのかを具体的に解説していきます。
省エネ設計では「UA値」ばかりが注目されがちですが、実はUA値とηAC値はまったく異なる目的の指標であり、両方を正しく考慮することが重要です。
UA値(外皮平均熱貫流率)は、冬の暖房期を想定し、建物からどれだけ熱が逃げやすいか(断熱性能)を示す数値です。
一方、ηAC値は、夏の冷房期を想定し、外部からどれだけ日射熱が室内に侵入するか(遮熱性能)を評価するものです。
つまり、UA値は「熱が出ていくのを防ぐ」性能、ηAC値は「熱が入ってくるのを防ぐ」性能。両者は全く逆の観点から建物のエネルギー効率を評価しているのです。
▶︎ 要点まとめ:
・UA値:冬の断熱評価(熱が逃げにくいか)
・ηAC値:夏の遮熱評価(熱が入りにくいか)
・どちらも一次エネルギー消費量に大きく影響
ηAC値が高すぎると、冷房の負荷が増え、一次エネルギー消費量が増加し、BEI値(省エネ性能の達成度)を悪化させてしまう可能性があります。
たとえUA値が基準を満たしていても、南面の窓が大きく、庇や遮蔽がなければηAC値が悪化し、最終的に基準不適合となるケースも少なくありません。
これからの省エネ設計では、UA値とηAC値の「バランスの取れた設計」が必須となります。
省エネ設計の現場では、「UA値が低ければOK」と考えられがちですが、それは冬の断熱性能だけを見ている状態です。
UA値は、建物全体の外皮(屋根・壁・窓など)から、どれだけ熱が外へ逃げにくいかを表す指標で、主に暖房期における熱損失の抑制を目的としています。
一方でηAC値は、夏の冷房期における日射熱の「入りにくさ」を数値化したもの。建物の開口部を通して、太陽からの熱がどれだけ侵入するかを評価します。
▼ つまり:
・UA値は「冬のエネルギー損失を防ぐ」
・ηAC値は「夏のエネルギー流入を防ぐ」
→ 双方のバランスが、省エネ設計の成否を左右します
たとえば、南面に大開口の窓を設けても、断熱性能が高ければUA値は問題なくクリアします。しかしその開口部がLow-Eガラスではなく、庇もないとなると、ηAC値は高くなり、冷房エネルギーが増加します。
つまり、「断熱性能」だけでなく、「日射の遮蔽」も計画段階から意識することが、省エネ性能の達成には不可欠なのです。
ηAC値に大きく影響するのは、建物の開口部(窓・ガラス)の面積や位置、遮蔽の有無です。
特に日射が強く当たる南面や西面の大開口では、庇や袖壁、Low-Eガラスなどの対策が取られていないと、ηAC値が急激に悪化し、冷房負荷の上昇につながります。
また、ηAC値の計算では、ガラスの種類(日射取得率)や、方位ごとの日射量、そして遮蔽部材の有無が数値に反映されるため、単なる面積計算ではなく、設計上の工夫が結果に直結します。
▼ ηAC値に影響する主な設計要素:
・窓の大きさと配置(特に南面・西面)
・ガラス種(遮蔽型Low-Eなど)
・庇や袖壁などの遮蔽装置の有無
・開口部周辺の植栽やバルコニーなど
また、意外と見落とされやすいのが東西面の開口部です。西日は特に強く、夏場の夕方には室温を一気に上げる要因になります。
南面だけでなく、東西の窓にも庇や外付けブラインドなどを組み合わせることで、ηAC値を効果的に抑えることができます。
次の章では、ηAC値を下げるために有効な設計テクニックについて、より具体的に解説していきます。
ηAC値の数値に最も大きな影響を与えるのが、窓の設計です。 単純な開口部の大きさだけでなく、「どの方位にどんなガラスを使い、どんな遮蔽物を設けているか」が、冷房期のエネルギー効率に直結します。
まず、日射の強い南面に大開口を設ける場合、庇やバルコニーがないと、夏の直射日光が室内に深く入り込み、ηAC値が高くなります。これにより、冷房負荷が一気に増加してしまいます。
また、使用するガラスの種類も重要です。遮蔽性能の高い「Low-E複層ガラス(遮蔽型)」を使えば、同じ窓サイズでもηAC値を大きく下げることができます。
▼ 設計時に特に注意すべき点:
・大きな窓には庇・袖壁を設ける
・遮蔽型のLow-Eガラスを採用する
・掃き出し窓や吹き抜けの上部窓は特に注意
庇の出幅や高さによって日射のカット率は大きく変わります。 設計初期段階で、開口部の構成とあわせて、日射遮蔽の「実効性」をセットで考えることが大切です。
次のセクションでは、南面以外の注意点や、簡単な見分け方について解説していきます。
ηAC値というと「南面の開口部が重要」と考えられがちですが、実際には東面・西面の窓が設計上の盲点になるケースが多く見られます。
特に西面は、夏場の夕方に強い日差しが差し込むため、冷房を使いたくなるタイミングで一気に室温が上昇します。遮蔽対策が不十分な西面の窓があると、ηAC値が高くなり、BEIにも悪影響を及ぼします。
また、朝日が入る東面も、寝室やリビングの温度上昇要因となることがあります。南面にだけ庇を設け、東西はノータッチという設計では、冷房負荷を抑えきれません。
▼ 南面以外の見直しポイント:
・西面の掃き出し窓は特に日射対策が必要
・東面も朝日が強く入るため、遮蔽を検討
・東西面は外付けブラインドや植栽が有効
簡易な見分け方としては、
・「直射日光が差し込む大きな窓がある」
・「日射遮蔽が無い or 弱い」
この2つが重なる場所は、ηAC値が上がりやすい“要注意ポイント”です。
次章では、こうした開口部に対して、どのような工夫をすればηAC値を効果的に下げられるか、具体的な設計対策を紹介していきます。
ηAC値は、設計の工夫によって確実に下げることができます。特に開口部の遮蔽設計・ガラス仕様の見直し・外構の活用が大きなポイントです。
以下では、ηAC値を改善するために有効な具体的手法を3つの観点から紹介します。
▼ 設計対策の3本柱:
1)ガラスの選定(Low-Eなど)
2)遮蔽設計(庇・袖壁・外付ブラインド)
3)外構・植栽など周辺環境の活用
これらをバランスよく組み合わせることで、ηAC値を下げつつ快適な住まいを実現することが可能です。
次の章では、それぞれの対策内容について、より詳しく解説していきます。
ηAC値の設計において最も大きな影響を与える要素のひとつが「窓ガラスの性能」です。とくにLow-Eガラスの選定は、冷房期における日射熱の侵入を防ぐために重要です。
Low-Eガラスには「日射遮蔽型」と「断熱型」があり、ηAC値に効果が高いのは日射遮蔽型です。これは、太陽光の中でも熱エネルギーに変換されやすい中赤外線領域の透過を抑えることで、室内への熱流入を大きく軽減します。
特に南面や西面の大開口においては、Low-Eガラスの「日射熱取得率(η値)」を確認し、できるだけ低い値のものを採用することが効果的です。
設計の段階でガラスの種類まで明記することで、完了検査時の適合や補助金申請時の整合性も確保しやすくなります。ガラス選定は、断熱だけでなく「日射遮蔽」の観点からも評価しましょう。
ηAC値を下げるためには、開口部からの日射をどれだけ遮るかが大きな鍵になります。Low-Eガラスと同様に、物理的な日射遮蔽の工夫も非常に効果的です。
代表的な対策としては、庇(ひさし)の設置が挙げられます。特に南面の窓においては、夏の高い太陽高度に対して庇が直射日光を遮ってくれるため、冷房負荷の軽減に直結します。
また、袖壁や、外付けブラインド・ルーバーなどの設置も、朝夕の斜めから差し込む日射を防ぐのに有効です。これらの遮蔽装置は、室内側のカーテンやブラインドよりも外部で遮るぶん、冷房効率を高める効果が大きくなります。
遮蔽設計は「美観」や「採光」とのバランスも求められますが、ηAC値を下げる観点では非常に重要な要素です。設計初期から意識し、建物形状との整合性も含めて検討することがポイントです。
ηAC値の改善は、窓やガラス、庇などの建築要素だけでなく、敷地周辺の外構計画によっても実現できます。
特に効果的なのが、落葉樹などの植栽を窓の外に配置する手法です。夏は葉が茂って日差しを遮り、冬は落葉して暖かな日差しを室内に届けてくれるという、自然を活かした遮蔽設計になります。
また、フェンスや格子、カーポートの屋根なども、窓に直射日光が当たるのを防ぐ「パッシブな遮蔽装置」として活用可能です。
▼ 外構を活かした遮蔽の工夫:
・落葉樹を南面・西面の窓前に植える
・カーポートやフェンスで日射を遮る位置に配置
・隣家や高低差を利用して日射をコントロール
これらの外構要素はηAC値の計算に直接は反映されませんが、実際の冷房負荷には大きく寄与します。
また、植栽による遮蔽は、視覚的な涼しさや快適さにもつながり、居住満足度を高める副次的な効果も期待できます。
次の章では、ηAC値が省エネ基準や等級制度とどう関係しているのかを解説していきます。
ηAC値は、建物の「冷房期のエネルギー性能」を左右する指標であり、断熱等性能等級6・7やBEI(一次エネルギー消費量)の評価にも密接に関係しています。
これまで等級4・5を中心に語られてきた断熱性能ですが、2022年以降に登場した等級6・7では、冷房期の遮蔽性能(=ηAC値)も重要視されるようになりました。
特に、南面や西面に大きな開口部がある住宅は、遮蔽対策を怠るとηAC値が高くなり、一次エネルギー消費量(BEI)が悪化して基準不適合となることがあります。
▼ ηAC値と制度の関係:
・等級6・7ではηAC値の管理が実質必須
・ηAC値が悪いとBEIも悪化しやすい
・BEI=一次エネルギー消費量の達成度を表す指標
たとえUA値で等級6をクリアしていても、ηAC値が高すぎると、冷房負荷が増え、BEIが基準を超えてしまう――というケースは現場でも頻発しています。
つまり、省エネ性能を証明するには「UA値+ηAC値」の両立が必要不可欠です。
次章では、ηAC値の基本と対策をふまえたうえで、設計のどの段階で何を意識すればよいのかを、改めてまとめていきます。
2022年に新設された断熱等性能等級6・7は、単にUA値を下げればよいという基準ではありません。
これらの上位等級では、UA値による断熱性能に加えて、冷房期の省エネ性能(ηAC値)も重要な評価対象となっています。
とくに等級7では、単に断熱材の性能や厚みを上げるだけでは足りず、日射遮蔽まで計画的に設計しなければ達成が難しい水準です。
▼ 等級6・7とηAC値の関係:
・UA値が良好でも、ηAC値が悪ければ等級を満たせない可能性あり
・庇やLow-E遮蔽型ガラス、外構などによる遮蔽設計が求められる
・冷房負荷のコントロールが等級達成のカギとなる
評価機関や自治体によっては、ηAC値が等級判定の参考値として活用されているケースも増えています。 このため、今後ますますηAC値を意識した設計が求められるようになるでしょう。
次は、ηAC値が一次エネルギー消費量(BEI)にどのように影響するかについて解説していきます。
ηAC値は、冷房期に建物がどれだけ日射熱を取り込むかを示す指標です。 そのため、ηAC値が高ければ高いほど、冷房に使われるエネルギー量が増加し、一次エネルギー消費量(BEI)に直接影響を与えます。
BEI(Building Energy Index)は、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で割った値であり、0.8以下で基準適合、0.6以下で上位等級などの指標を満たすことができます。
このBEIは、冷暖房・給湯・換気・照明など全体の消費量で評価されるため、ηAC値が高い設計では冷房負荷が増え、BEIが基準を超えてしまうリスクが高くなります。
▼ ηAC値がBEIに与える影響:
・冷房期の電力量が増加することでBEIが悪化
・BEIを抑えるためにηAC値を下げる設計が有効
・日射遮蔽が不十分だと、他の設備で補っても限界あり
BEIは補助金や評価制度の基準値とも連動しているため、ηAC値の改善は「設計・評価・申請」すべてにおいてメリットがあります。
次章では、ここまでのポイントをまとめながら、ηAC値を設計にどう活かすべきかを振り返ります。
ηAC値は、これまで見落とされがちだった「冷房期の省エネ性能」を示す重要な指標です。
断熱性能を示すUA値だけでなく、夏の日射にどう対応するかという視点を設計に取り入れることが、これからの省エネ基準や等級達成には欠かせません。
遮蔽型Low-Eガラスの選定、庇や袖壁の配置、外付ブラインドや植栽の活用――こうした設計上の工夫が、ηAC値を改善し、BEI値の達成にもつながります。
▼ 設計者が今後意識すべきこと:
・UA値とηAC値はセットで考える
・開口部の配置と方位に日射遮蔽を組み込む
・BEIを意識し、断熱+遮熱のバランスを設計する
これからの住宅設計では、「夏の涼しさ」も評価される時代です。 ηAC値をうまくコントロールすることで、省エネ性能だけでなく、快適性・光熱費削減・補助金対応など、さまざまな面で価値を高めることができます。
ぜひ、ηAC値という視点を武器に、これからの冷房設計に取り組んでみてください。
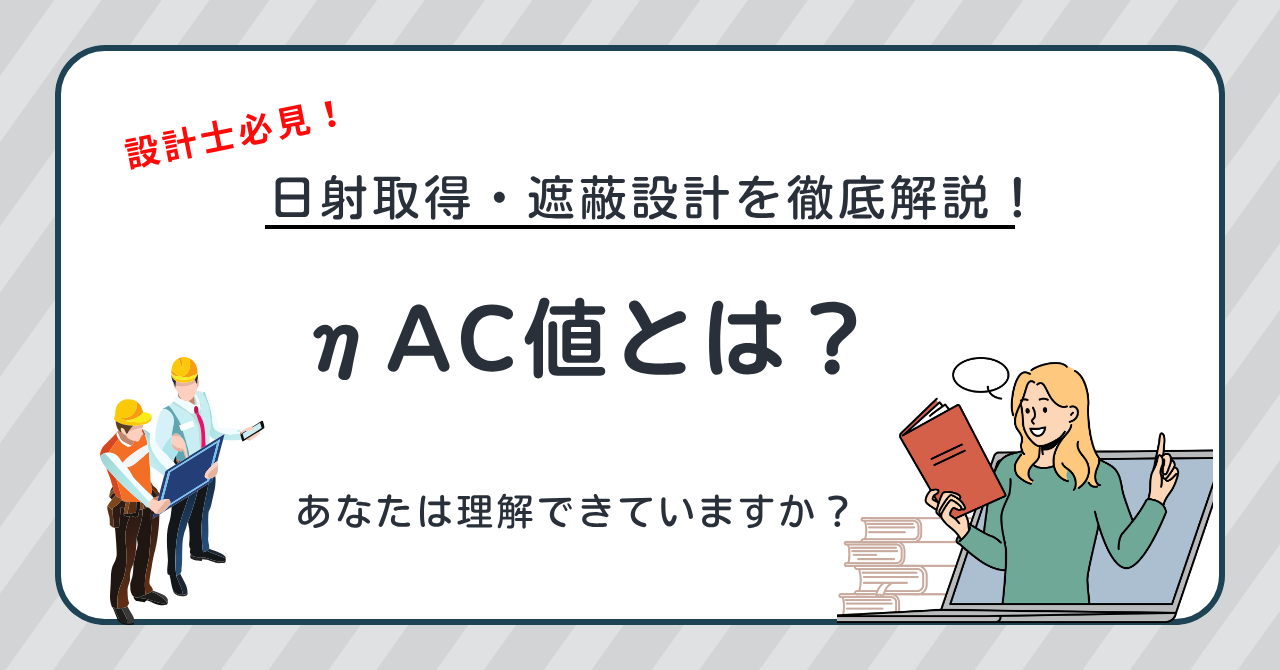


コメント